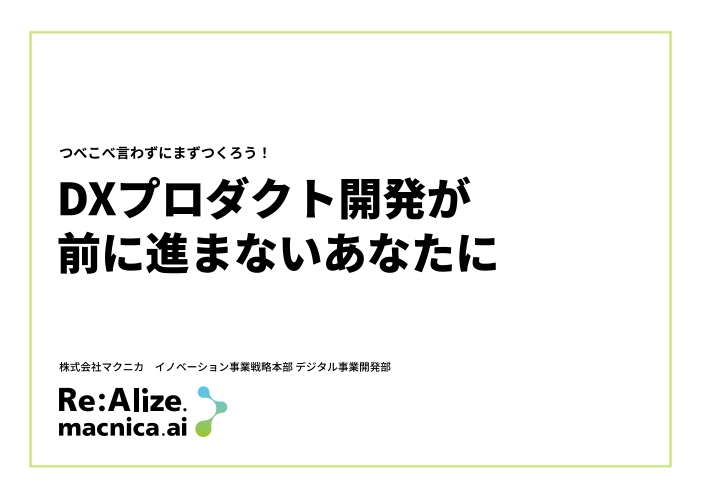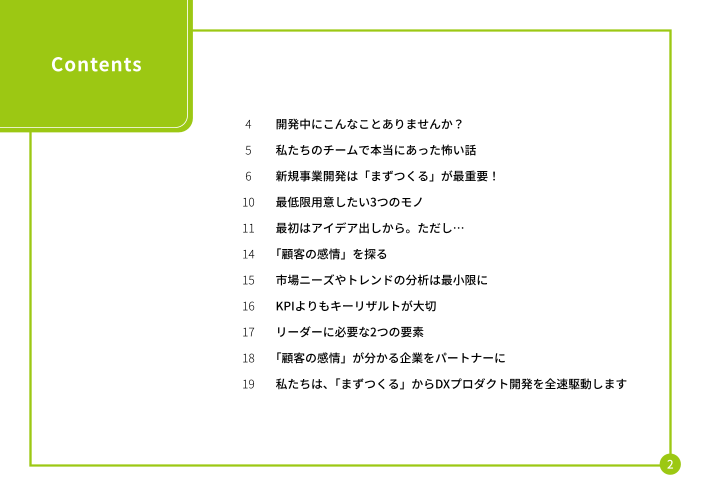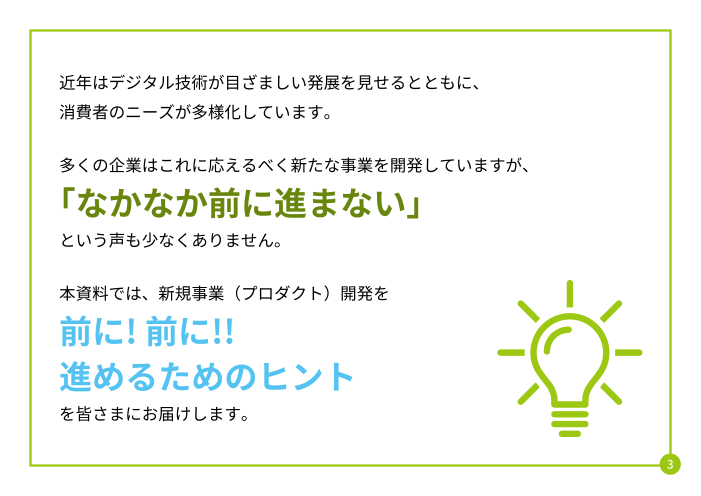1/20ページ
ダウンロード(2.9Mb)
多様化する消費者のニーズに応え、さらなる企業価値向上や成長を図るためには、新規事業開発が欠かせません。一方でその実践ハードルは高く、「プロジェクトが前に進まない」「何から始めればよい か分からない」ということも決して少なくないかと思います。本資料では、新規事業(プロダクト)開発を前に!前に!!進めるためのヒントを皆さまにお届けします。
このカタログについて
| ドキュメント名 | DXプロダクト開発が前に進まないあなたに |
|---|---|
| ドキュメント種別 | ホワイトペーパー |
| ファイルサイズ | 2.9Mb |
| 取り扱い企業 | 株式会社マクニカ (この企業の取り扱いカタログ一覧) |
この企業の関連カタログ

このカタログの内容
Page1
つべこべ言わずにまずつくろう!
DXプロダクト開発が
前に進まないあなたに
株式会社マクニカ イノベーション事業戦略本部 デジタル事業開発部
Page2
Contents
4 開発中にこんなことありませんか?
5 私たちのチームで本当にあった怖い話
6 新規事業開発は「まずつくる」が最重要!
10 最低限用意したい3つのモノ
11 最初はアイデア出しから。ただし…
14 「顧客の感情」を探る
15 市場ニーズやトレンドの分析は最小限に
16 KPIよりもキーリザルトが大切
17 リーダーに必要な2つの要素
18 「顧客の感情」が分かる企業をパートナーに
19 私たちは、「まずつくる」からDXプロダクト開発を全速駆動します
2
Page3
近年はデジタル技術が目ざましい発展を見せるとともに、
消費者のニーズが多様化しています。
多くの企業はこれに応えるべく新たな事業を開発していますが、
「なかなか前に進まない」
という声も少なくありません。
本資料では、新規事業(プロダクト)開発を
前に! 前に!!
進めるためのヒント
を皆さまにお届けします。
3
Page4
開発中に
こんなこと
ありませんか? 「何が本質的な課題なんだっけ…?」
とずっと話している
調査を繰り返すばかりで、
「何をつくるか」を決められない
前には進むが、「課題の解像度が上がった」を
進捗と捉えて満足することが多く、
スピード感がない
4
Page5
私たちのチームで
本当にあった
怖い話 私たちも、失敗を経験しました
プロジェクトで ロジックツリーが 何も完成せず、
仮説の深掘りを 無限大に いつの間にか1年が
繰り返すうちに… 膨れ上がり… 経過してしまった!
5
Page6
新規事業開発は
「まずつくる」
が最重要!
私たちがもっとも伝えたいメッセージは、
「新規事業開発は、まずつくる!」
これに尽きます。
6
Page7
新規事業開発は「まずつくる」が最重要!
なぜ「まずつくる」が大事? ①
そもそも仮説検証にはキリがなく、
「やってみなければ分からない」ことが
あまりにも多いからです。
実際に動くモノを「まずつくる」ことをベースとし、
それと情報整理を並行して行うことで仮説の解像度が高まり、
そのモノの価値が最大化されると私たちは考えています。
また、つくったモノを実際にユーザーに触ってもらうことで
さまざまなフィードバックを得られ、当初は気づいていなかった課題や、
潜在ニーズを掘り起こせることもあります。
7
Page8
新規事業開発は「まずつくる」が最重要!
なぜ「まずつくる」が大事? ②
関係者(ステークホルダー)とのコミュニケーション形成においても、
「まずつくる」ことが重要です。
実際に動くモノをつくって提示することは、
責任者や決済者に進捗を見える化して伝える役割を果たし、
双方が安心と信頼を得ながらプロジェクトを円滑に進めやすくなります。
またスタートアップの資金調達においても、
出資者に実際に動くモノを見せることができれば、
出資を集められる可能性は高くなると考えられます。
8
Page9
新規事業開発は「まずつくる」が最重要!
「まずつくる」で、私たちはこんなに変わった!!
まず動くモノを
つくろう!
何日かかる??
3日で
いけます!
1年くらいかけて
「まずつくる」で仮説検証や 何もできなかったのに、
開発を進めた結果… 3 ヶ月くらいで動く!!
9
Page10
最低限
用意したい
3つのモノ 「まずつくる」ときは、
これらを用意しましょう
ワイヤーフレーム付きUI 最小限動作するシステム 集客用LP
ユーザーにUIを見せることで 実際に動くシステムを触ってもらって、 幅広くユーザー(リード)を
方向性のすり合わせができ、 購入意思決定のフィードバックを得ます。 集めるために、コンテンツを
仮説の解像度が向上します。 隠れた課題やニーズが見つかることも。 配置したページが必要です。
参考URL
https://www.macnica.co.jp/business/ai/
published/realize_ui/
10
Page11
最初はアイデア
出しから。 最短ルートをたどりましょう!
ただし…
プロジェクト開始後、最初は基本的にアイデア出しから始めることになるでしょ
う。ただし仮説検証には正解がないため、議論にばかり時間を費やすわけにも
いきません。
私たちは「まずつくる」際に、チームで “あるシート” を埋め、そこで出たアイ
デアを形にするというやり方を採用しています(シートのひな型は次ページ)。
記載する内容は
「タイトルと概要」「提供価値」
「誰がどんな課題に対して買うか」
の3つだけです。
この方法で1時間の会議中に10個以上のプロダクト案を出し、エンジニアが2 ~
3日で動くモノをつくり、顧客に見せてフィードバックをもらう…というサイク
ルが、私たちの中では完成しています。
11
Page12
ひな形
プロダクトタイトル
プロダクトの概要を入力します。プロダクトの概要を入力
します。プロダクトの概要を入力します。プロダクトの概
要を入力します。プロダクトの概要を入力します。プロダ
クトの概要を入力します。プロダクトの概要を入力します。
プロダクトの概要を入力します。プロダクトの概要を入力。 画像
提供価値
顧客に対しての提供価値を入力します。顧客に対しての提供価値
を入力します。顧客に対しての提供価値を入力します。顧客に対
しての提供価値を入力します。顧客に対しての提供価値を入力し
ます。顧客に対しての提供価値を入力します。 画像の補足を入力します。
誰がどんな課題に対して買うプロダクト?
● 誰がどんな課題に対して買うプロダクトかを入力します。
● 誰がどんな課題に対して買うプロダクトかを入力します。 画像 画像
● 誰がどんな課題に対して買うプロダクトかを入力します。
● 誰がどんな課題に対して買うプロダクトかを入力します。
● 誰がどんな課題に対して買うプロダクトかを入力します。 画像の補足を入力します。 画像の補足を入力します。
12
Page13
プロダクトタイトル
プロダクトの概要を入力します。プロこダクトの概要を入力
します。プロダクトの概要を入力します。のプロひダクなトの型概 をつくって、
要を入力します。プロダク会トの議概要でを入実力しま際す。にプロ使ダってみましょう!
クトの概要を入力します。プロダクトの概要を入力します。
プロダクトの概要を入仮力し説ます。検プロ証ダクはトのつ概要くを入力っ。てから行えばO画K像!
提供価値 まずはたくさんのアイデアを
顧客に対しての提供価値を入力します。顧客に対しての提供価値
を入力します。顧客に対しての提供価値を出入力しすますこ。顧客とに対も大事です!
しての提供価値を入力します。顧客に対しての提供価値を入力し
ます。顧客に対しての提供価値を入力します。 画像の補足を入力します。
誰がどんな課題に↓対しひてな買う形プロ(パダワクートポ?イントファイル)はこちら↓
● 誰がどんな課題に対して買うプロダクトかを入力します。
● 誰がどんな課題に対しクて買リうプロッダクトかでを入力ダしまウす。ンロードが画始像まります 画像
● 誰がどんな課題に対して買うプロダクトかを入力します。
● 誰がどんな課題に対して買うプロダクトかを入力します。
● 誰がどんな課題に対して買うプロダクトかを入力します。 画像の補足を入力します。 画像の補足を入力します。
13
Page14
「顧客の感情」
を探る つくったら、見せてみる!
「まずつくる」でモノを用意できたら、
それをユーザー(顧客)に見せつつ話すことも非常に重要です。
たとえば「何に困っていますか?」「どうすればこれを買ってくれますか?」
という風に質問をすると、相手から
「実は○○の悩みがあって…」「ここがもっと○○だったら…」など、
有益なフィードバックを得られる
可能性が高いでしょう。
反対に「この機能、どうですか?」「ニーズや興味がありますか?」という質問
は、相手から得られる回答の内容に具体性を期待できないため、好ましくあり
ません。
「顧客の感情」は開発における宝物です。積極的に探ってみましょう。
14
Page15
市場ニーズや
トレンドの分析 やはり時間を使うべきは「まずつくる」こと!
は最小限に
市場ニーズやトレンドの分析は確かに重要ですが、
割くリソースは最小限にとどめたいものです。
なぜなら仮説の段階である程度の予測はできても、
完全に読み切ることはまず不可能であり、結果として
分析し続けることが仮説検証を止める
(開発を遅くする)要因にもなり得るからです。
たとえばトイレのウォシュレットはもともと高齢者向けにつくられたものだそう
以下のような ですが、結果的にはあらゆる年代の人が利用しています。
分析専門サービスの 開発者は、当初からこのニーズを予測していたでしょうか。
活用もおすすめです
https://jp.ub-speeda. 市場価値やニーズは、仮説検証の最中やサービスのリリース後にきっと見え
com/ てきます。貴重な時間は「まずつくる」ことに充て、プロジェクトを進めな
がら解像度を上げていきましょう。
15
Page16
KPIよりも
キーリザルトが 現場は数字よりも目の前の進捗にこだわる!
大切
開発はスタートしたものの、「○年までに売上目標○○円」「アクティブユーザー○
人獲得」などのKPIだけが先に決められ、モノが完成しないので評価されなかっ
た…という経験はないでしょうか。
新規事業開発で非常に重要なのが、現場が優先的に意識し、かつ評価の対象と
してもらうべきは、大局的なKPIではなく、
開発の進捗などを目標とした
「キーリザルト」であるということです。
これを実現するためには、1ヶ月や3ヶ月などなるべく短いタームで関係者(ステー
クホルダー)とキーリザルトを合意し、常に進捗を明確にすることが必要です。
そして、そのために不可欠なのが…そう。「まずつくる」ことです。
チームの努力の結晶を見せて、しっかり納得してもらいましょう。
16
Page17
リーダーに
必要な
2つの要素 とにかく早い決断で
チームを引っ張る
意思決定を早くする 「失敗や経験から学ぶ」という
マインドセットをもつ
新規事業開発は、プロジェクトを 1 本に絞 「失敗したらどうしよう」「過去に○○で成功
ると立ちいかなくなった際のリスクが大きい したから今回も…」という消極的な意識は、
ものです。 開発の進捗を鈍らせます。
そのため、リーダーには「3 人に手応えを 新規事業開発ではすべて
訊いてみて、色良い返事がなければ開発を が学びの糧だという心
諦める」など、素早く判断を下せる決断力や、 構えで、「まずつくる」
進退を決める明確な線引きをしておくこと を 率 先 し て 実 行 し ま
が求められます。 しょう。
17
Page18
「顧客の感情」
が分かる企業を
パートナーに 良質なフィードバックは、
開発の宝
新規事業開発でパートナーを募る場合には、
「質のよいユーザー
フィードバックを得ること」
を優先してくれる企業を信頼するとよいでしょう。
先述のように「顧客の感情」は開発にとっての宝物であり、
それを多く集めるほどつくるモノの価値が高くなるからです。
反対に「新規事業のフレームワークをたくさんもっています!これに沿って進め
ましょう!」など、機械的に進行するコンサルタントには注意が必要です。
18
Page19
私たちは、「まずつくる」から
DXプロダクト開発を全速駆動します
PHILOSOPHY WHAT WE DO
私たちの考える共創基盤 アイデアに火を灯すために
未知の領域に挑戦する新規事業の成功に必要なのは、
お客様 “共に歩むパートナー”と “専門知識”
● 共創事業拡大に向けた
● 社会課題を解決したいと 新規事業の成功には、多岐にわたるプロフェッショ
顧客プラットフォーム 経験・手法・ ナルの知見が必要です。
いう想い、パーパス ノウハウ
● デジタル人財を網羅した 私たちは「価値創造型プロフェッショナル集団」で
● 解決するための プロフェッショナル チームを編成し、アイディエーション、ペルソナ・
実現アイデア お客様 ジャーニー設計、事業計画策定、テクノロジ一実装
● 350件以上の実装経験をもつ など、事業を成功に導くための様々な工程を共に実
● 深い業界ナレッジ 技術アセット カルチャー プロフェッ
ショナル 現します。
未知の領域に挑戦し、ビジネスの可能性を広げましょう!
APPROACH DXプロダクト開発は、まずつくる!これに尽きます。実際に動くモノを「まずつくる」
DXプロダクト開発を成功に導く進め方 ことをベースとし、それと情報整理を並行して行うことで仮説の解像度を上げ、プロダ
クトの価値を最大化していきます。
1 企画・
MVP開発 2 ユーザー 3 複数ユーザー 4 グロース・
価値検証 獲得・機能改善 機能拡充
事業企画→ 課題の特定→ サービスローンチ→ 本格展開→
初期プロダクト α版プロダクト β版プロダクト 正式プロダクト
まずつくる! すぐつくる! もっとつくる! リリース!
テスト テスト ファースト アクティブ
ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー
19
Page20
第一版 2023年7月
株式会社マクニカ
〒222-8561 横浜市港北区新横浜 1-6-3
マクニカ第1ビル
Tel :045-470-9118
Mail : consulting-iot@macnic.co.jp
Web: https://www.macnica.co.jp/
business/ai/manufacturers/
realize/
©Macnica, Inc. All rights Reserved.