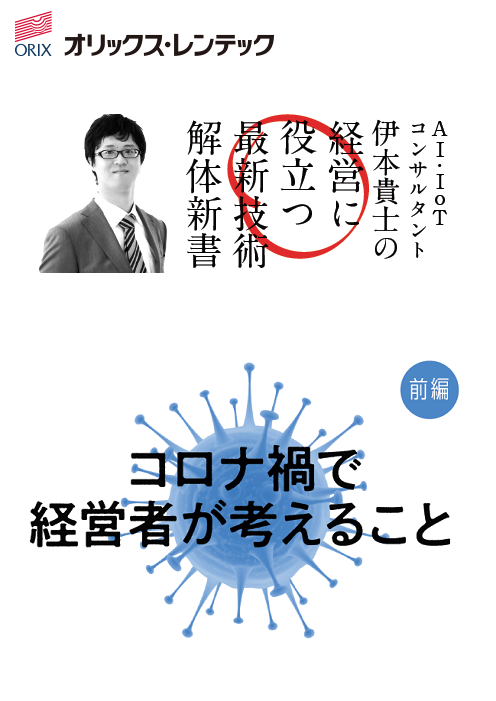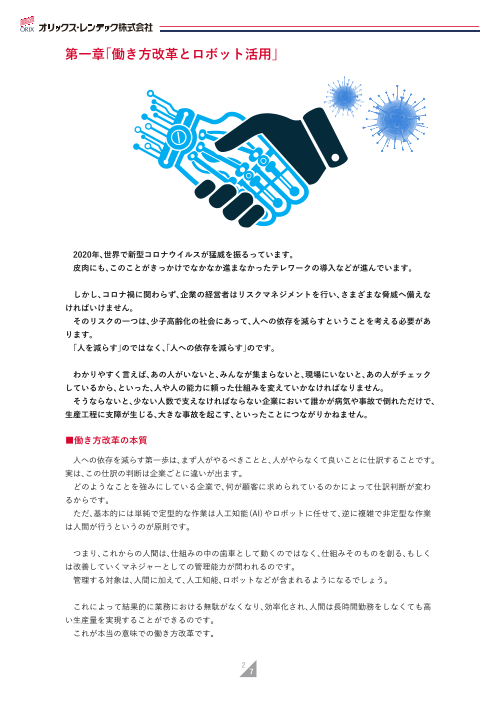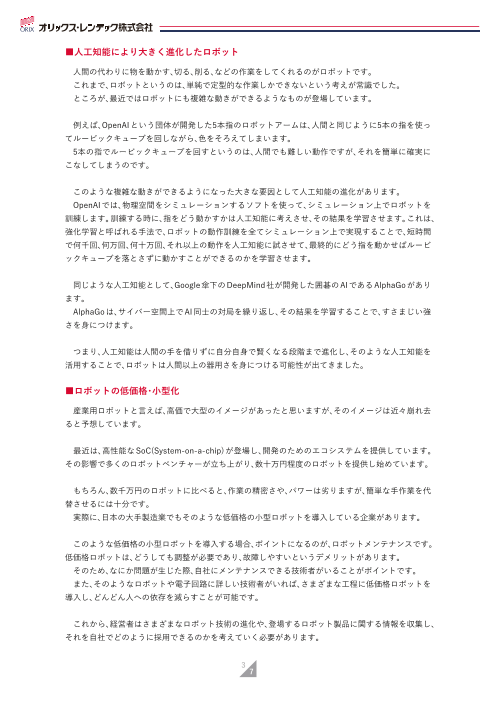1/7ページ
ダウンロード(989.5Kb)
2020年、世界で新型コロナウイルスが猛威を振るっています。 皮肉にも、このことがきっかけでなかなか進まなかったテレワークの導入などが進んでいます。
しかし、コロナ禍に関わらず、企業の経営者はリスクマネジメントを行い、さまざまな脅威へ備えなければいけません。
リスクとして少子高齢化など、人への依存を減らすということを考える必要があります。
今回、メディアスケッチ代表取締役 兼 サイバー大学専任講師、AI/IoTコンサルタントの伊本貴士氏による経営視点でのコロナ対策について紹介します。
このカタログについて
| ドキュメント名 | コロナ禍で経営者が考えること (前編) | AI・IoTコンサルタント 伊本貴士の経営に役立つ最新技術解体新書 |
|---|---|
| ドキュメント種別 | ホワイトペーパー |
| ファイルサイズ | 989.5Kb |
| 取り扱い企業 | オリックス・レンテック株式会社 (この企業の取り扱いカタログ一覧) |
この企業の関連カタログ

このカタログの内容
Page1
解最役経伊コAンI
体新立営本サ・貴ルI
新技つに士タ
o
ンT
書術 のト
前編
コロナ禍で
経営者が考えること
第一章:働き方改革とロボット活用
第二章:コロナ禍を乗り越えるために必要な五つの改革
執筆者 伊本 貴士(いもと たかし)
メディアスケッチ株式会社代表取締役。IoTやAIなど、最新技術のコンサルティングサービスを
提供。製造業や建設業などを中心に企業のアドバイザーや技術顧問を務める。また、スマートシ
ティの専門家として地方自治体のアドバイザーや補助金審査員なども務めている。人材教育分
野においても、サイバー大学専任講師や日経ビジネススクール、日経xTech塾などの講師も務める。
スマートシティや最新技術の評論家として、各地で講演をする傍らメディアにも出演。(フジテ
レビ・ホンマでっか!?TV、テレビ朝日・サンデーLIVE!!、TBS・あさチャン!など)
1
7
Page2
第一章「働き方改革とロボット活用」
2020年、世界で新型コロナウイルスが猛威を振るっています。
皮肉にも、このことがきっかけでなかなか進まなかったテレワークの導入などが進んでいます。
しかし、コロナ禍に関わらず、企業の経営者はリスクマネジメントを行い、さまざまな脅威へ備えな
ければいけません。
そのリスクの一つは、少子高齢化の社会にあって、人への依存を減らすということを考える必要があ
ります。
「人を減らす」のではなく、「人への依存を減らす」のです。
わかりやすく言えば、あの人がいないと、みんなが集まらないと、現場にいないと、あの人がチェック
しているから、といった、人や人の能力に頼った仕組みを変えていかなければなりません。
そうならないと、少ない人数で支えなければならない企業において誰かが病気や事故で倒れただけで、
生産工程に支障が生じる、大きな事故を起こす、といったことにつながりかねません。
■働き方改革の本質
人への依存を減らす第一歩は、まず人がやるべきことと、人がやらなくて良いことに仕訳することです。
実は、この仕訳の判断は企業ごとに違いが出ます。
どのようなことを強みにしている企業で、何が顧客に求められているのかによって仕訳判断が変わ
るからです。
ただ、基本的には単純で定型的な作業は人工知能(AI)やロボットに任せて、逆に複雑で非定型な作業
は人間が行うというのが原則です。
つまり、これからの人間は、仕組みの中の歯車として動くのではなく、仕組みそのものを創る、もしく
は改善していくマネジャーとしての管理能力が問われるのです。
管理する対象は、人間に加えて、人工知能、ロボットなどが含まれるようになるでしょう。
これによって結果的に業務における無駄がなくなり、効率化され、人間は長時間勤務をしなくても高
い生産量を実現することができるのです。
これが本当の意味での働き方改革です。
2
7
Page3
■人工知能により大きく進化したロボット
人間の代わりに物を動かす、切る、削る、などの作業をしてくれるのがロボットです。
これまで、ロボットというのは、単純で定型的な作業しかできないという考えが常識でした。
ところが、最近ではロボットにも複雑な動きができるようなものが登場しています。
例えば、OpenAIという団体が開発した5本指のロボットアームは、人間と同じように5本の指を使っ
てルービックキューブを回しながら、色をそろえてしまいます。
5本の指でルービックキューブを回すというのは、人間でも難しい動作ですが、それを簡単に確実に
こなしてしまうのです。
このような複雑な動きができるようになった大きな要因として人工知能の進化があります。
OpenAIでは、物理空間をシミュレーションするソフトを使って、シミュレーション上でロボットを
訓練します。訓練する時に、指をどう動かすかは人工知能に考えさせ、その結果を学習させます。これは、
強化学習と呼ばれる手法で、ロボットの動作訓練を全てシミュレーション上で実現することで、短時間
で何千回、何万回、何十万回、それ以上の動作を人工知能に試させて、最終的にどう指を動かせばルービ
ックキューブを落とさずに動かすことができるのかを学習させます。
同じような人工知能として、Google傘下のDeepMind社が開発した囲碁のAIであるAlphaGoがあり
ます。
AlphaGoは、サイバー空間上でAI同士の対局を繰り返し、その結果を学習することで、すさまじい強
さを身につけます。
つまり、人工知能は人間の手を借りずに自分自身で賢くなる段階まで進化し、そのような人工知能を
活用することで、ロボットは人間以上の器用さを身につける可能性が出てきました。
■ロボットの低価格・小型化
産業用ロボットと言えば、高価で大型のイメージがあったと思いますが、そのイメージは近々崩れ去
ると予想しています。
最近は、高性能なSoC(System-on-a-chip)が登場し、開発のためのエコシステムを提供しています。
その影響で多くのロボットベンチャーが立ち上がり、数十万円程度のロボットを提供し始めています。
もちろん、数千万円のロボットに比べると、作業の精密さや、パワーは劣りますが、簡単な手作業を代
替させるには十分です。
実際に、日本の大手製造業でもそのような低価格の小型ロボットを導入している企業があります。
このような低価格の小型ロボットを導入する場合、ポイントになるのが、ロボットメンテナンスです。
低価格ロボットは、どうしても調整が必要であり、故障しやすいというデメリットがあります。
そのため、なにか問題が生じた際、自社にメンテナンスできる技術者がいることがポイントです。
また、そのようなロボットや電子回路に詳しい技術者がいれば、さまざまな工程に低価格ロボットを
導入し、どんどん人への依存を減らすことが可能です。
これから、経営者はさまざまなロボット技術の進化や、登場するロボット製品に関する情報を収集し、
それを自社でどのように採用できるのかを考えていく必要があります。
3
7
Page4
ロボットを可能な限り活用し、人への依存度を減らすことで、人間はよりリスクマネジメントやクリ
エーティブな業務に時間を割くことができ、新しい事業を生み出すための余裕を生み出す第一歩とな
ります。
そのような効率化なしにイノベーションはあり得ません。
第二章「コロナ禍を乗り越えるために必要な五つの改革」
新型コロナウイルスが世界中に広まり経済にもかなり大きな影響を与えています。
この出来事はビジネス環境を大きく変えようとしています。
購買意欲、労働環境、価値観などさまざまなものが、新型コロナウイルスのまん延をきっかけとして
変化し、まさにこれからパラダイムシフトが発生すると思います。
企業は、これまでと同じ活動を行うことで利益を確保することは難しく、とはいえ自宅待機が続き今
後の先行きに不安を感じている人が多いかもしれません。
■経営において最重要の指標
このような世界的に経済が混乱している状況下では、キャッシュフローの最適化が非常に重要です。
当たり前ですが、現金がなければ何もできません。これまでは銀行からの借り入れや株式の売却によ
って現金を調達することが容易でしたが、これからは難しくなることも想定しなければいけません。
よって、赤字で改善が見込めない事業は早期に撤退し、黒字となる事業を生み出すことが重要です。
よって、これから最も重要な指標は「利益率」ではないでしょうか。
急速に変化する情勢の中で、迅速で確実に利益を確保するには、これまでにない柔軟な組織を構築す
る必要があります。
短期間で何度もプロトタイプを作り販売テストを行って、自分たちができる高利益ビジネスを探し
ていかなければなりません。
4
7
Page5
今まで通り、それぞれが自分の仕事だけを意識し、毎日同じことをやれば良いという少品種大量生産
を続け、薄利多売を行っている企業は間違いなく行き詰まるでしょう。
■超柔軟組織を構築するために必要な五つの改革
私のさまざまな企業へイノベーションを推進するためのコンサルティングを行った経験から、超柔
軟組織には以下の改革が必要になります。
・プロジェクト組織への移行
・探索型製品開発
・正しい指標の設定
・モニタリング
・ダイナミックな情報共有
基本的には、これまでにも書いたように、「データ・ドリブン」「リーン思考」という考え方をベースに、
無駄なく確実に進む方向を間違えないというのが原則です。
無駄なくというのは、生産活動だけではなく、組織運営や外部との交渉や取引、会議までさまざまな
箇所に及ぶことに気をつけてください。
■組織運営のイノベーション
「プロジェクト組織への移行」というのは、従来の役割ごとにグループ化した組織から、目的ごとにグ
ループ化した組織へと変わることです。
急速に変化する社会においては、企業におけるミッションは次々と変わります。
それに合わせて、イノベーションごとにプロジェクト組織をつくり、そこにさまざまなエキスパート
が集まり一つの目標に向かって活動していく手法です。
この組織体系は、会社のミッション(=社会の需要)に合わせて柔軟に変化するというのが理想なので、
都度変わるようにしなければいけません。
実は、コンサルタントの世界はすでにこのような組織体系になっています。
基本的に部というものが存在せず、ミッションごとに最適な人員を集めて組織編成します。
そのためには、個々の社員が自分は何に秀でていて、何ができる人間かを明確にする必要があり、そ
のため、何をやっているのかよくわからない人というのは存在しません。
これからの時代において「役職」というのは、役割を示すものです。地位を示すものではありません。
社長が一番偉いなんてことはなく、社長は社長という経営をとりまとめる役割を担っている人です。こ
の従来と違う考え方が受け入れることができない社員が多くいるかもしれません。それに対してトッ
プが強いメッセージで時代が変化しているということを示しつつ人事評価などのやり方を抜本的に変
えていく必要があります。
■開発のイノベーション
「探索型製品開発」というのは、これまでも書いたリーン思考的な製品開発のことですが、売れる商品
というのはマーケティング調査などでは時間がかかりすぎる上に正確ではないという前提の元に、と
りあえず開発して世の中に出してみるという製品開発手法です。
この時に重要なのは、製品開発に対するリスク管理を行うことです。わかりやすく言えば、開発にあ
5
7
Page6
まり時間とお金をかけることなく、必要最低限の機能で世の中に出すということをしなければなりません。
例えば、スマートスピーカーというものが世の中に出ていますが、最初は話かけても賢い返事はなく
音楽をかけるくらいしかできませんでした。あれは、まさに世の中にスマートスピーカーというものが
世の中に必要とされているかを試しているのだと思います。社会が必要とするならば、スマートスピー
カーは新しいバージョンになる度により賢く便利になるでしょう。GoogleやAppleといった企業が世
の中に出した製品でも、すでに販売を取りやめたものが多々あります。これは、世の中が求めていない
とわかったものがすぐに開発をやめて新しいものをまた探索しつつ開発する。これが探索型製品開発
という考え方です。
■効果検証のイノベーション
「正しい指標の設定」というのは、自分たちの「利益」(売上ではなく利益)につながる確かな指標とい
うものをモニタリング対象として定めるというものです。
例えば、お弁当を売っているお店を経営しているとしましょう。この場合、1日の販売数はその店舗の
成果を反映しているように見えますが、実は成果を計るには正しい指標とは言ません。
なぜなら、大きな店舗、人が多い地域なら数が多く売れて当然です。また、多く売ってもそれ以上に多
くの人件費が必要となり、多くの売れ残りがあると売上は多くても赤字である場合もあります。
このように、一見成果につながっているように見えても実際にはつながっていない指標を「虚栄の指標」
と言います。世の中には、売上50%アップといった「虚栄の指標」に対する目標に向かって活動してい
る企業が多く、その場合、頑張っても実際には手元にキャッシュが残らず苦しい経営になります。
本当に、その指標が会社の利益に結びついているのか。この視点が重要です。
「モニタリング」というのは、まさにこれまでにも述べた計測のことです。可能な限り、あらゆる活動
を見える化すべきです。それによって、正しい情報やデータを元に分析することができます。
もちろん、センシングによって生産活動を見える化し、生産効率をモニタリングすることは今や製造
業における必須条件と言えるでしょう。
また、お金の流れを「見える化」することも重要です。実はこれができていない企業が非常に多くあります。
どこへ、どれだけのお金を支払って、どの製品にどれだけのコストが必要となって、どこにどれだけの
お金を支払っているのかといったことを可能な限り細かくモニタリングできるようにします。
論理的な視点で考えると、その製品を開発するのに必要な間接費が全てわかれば、どの製品が赤字で
その製品が黒字かが一目瞭然で、黒字のものだけ作れば会社は黒字のはずです。
■情報共有のイノベーション
「ダイナミックな情報共有」とは、プロジェクト制の組織において、円滑で効率の良い情報共有は非常
に重要です。会議室の会議などは効率良いとは言ません。Zoomなどを使ったテレビ会議システムで十
分です。これからはツールを使って情報共有を行うことが原則です。具体的には、Slack(https://slack.
com/)のようなグループチャットができるツールがIT業界では人気です。また、Trello(https://trello.
com/)といった「かんばん方式」のツールもあります。Microsoft社のTeams(https://www.microsoft.
com/ja-jp/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software)などはワードやエクセルといった
Officeソフトとの連携も考えられており、業務を円滑に進めることができます。
このようなツールを使うと、プロジェクトごとや役割ごとにグループを自由に作って、参加者をグル
ープごとに設定できるので、必要な人に迅速に情報共有ができ、なおかつ組織が変わってもすぐに対応
することができます。
6
7
Page7
新型コロナウイルスの影響で閉塞(へいそく)感が出ている状況ですが、実は今だからやるべきこと、
やれることがたくさんあります。
このような状況下で、会議をテレビ会議にする、情報ツールで情報共有をするといった改革を行うこと
に反対する人はいないでしょう。
特に、これから企業をマネジメントする立場の方々には、これから何が必要とされるのか、それを迅
速になおかつ確実に遂行するには何を変えていかなければならないのかを計画し、マイルストーンを
設定し示すことが必要となります。
みんなが危機感を持つ今だからこそ、いろいろ新しいことを試すことができるのではないでしょうか?
解最役経伊コAンI
体新立営本サ・貴ルI
新技つに士タ
o
ンT
書術 のト
コロナ禍で経営者が考えること(前編)前編
コロナ禍で
経営者が考えること
本 件 に 関 する お 問 い 合 わ せ 先
https://www.orixrentec.jp/
〒141-0001 東京都品川区北品川五丁目5番15号 大崎ブライトコア
7
7