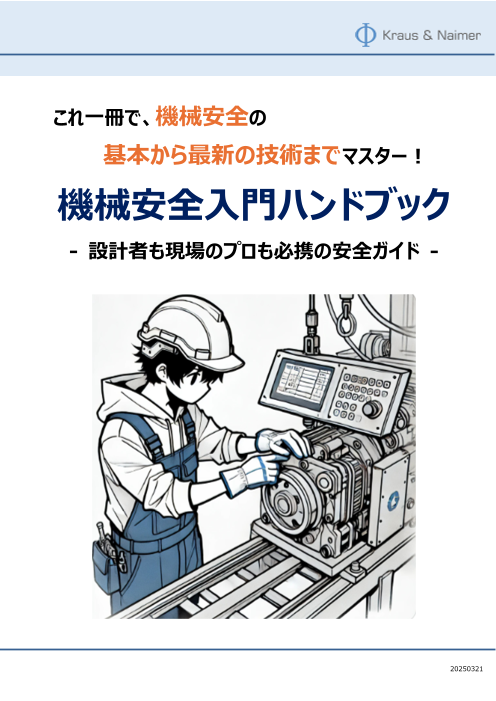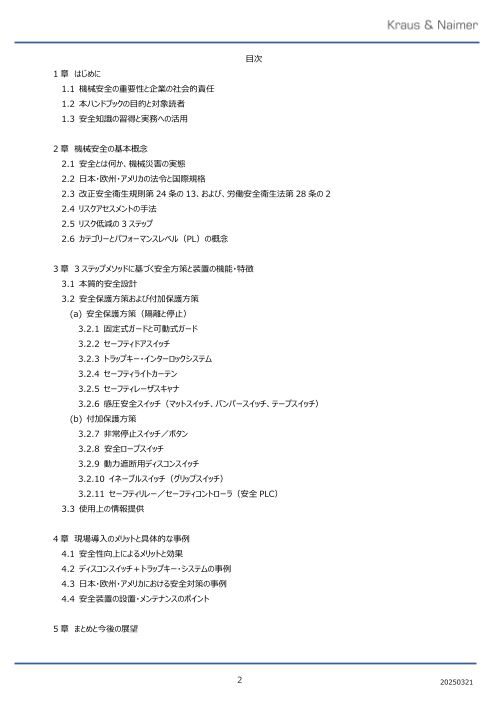これ⼀冊で、機械安全の
基本から最新の技術までマスター︕
機械安全⼊門ハンドブック
- 設計者も現場のプロも必携の安全ガイド -
20250321
目次
1 章 はじめに
1.1 機械安全の重要性と企業の社会的責任
1.2 本ハンドブックの目的と対象読者
1.3 安全知識の習得と実務への活⽤
2 章 機械安全の基本概念
2.1 安全とは何か、機械災害の実態
2.2 ⽇本・欧州・アメリカの法令と国際規格
2.3 改正安全衛⽣規則第 24 条の 13、および、労働安全衛⽣法第 28 条の 2
2.4 リスクアセスメントの⼿法
2.5 リスク低減の 3 ステップ
2.6 カテゴリーとパフォーマンスレベル(PL)の概念
3 章 3 ステップメソッドに基づく安全⽅策と装置の機能・特徴
3.1 本質的安全設計
3.2 安全保護⽅策および付加保護⽅策
(a) 安全保護⽅策(隔離と停⽌)
3.2.1 固定式ガードと可動式ガード
3.2.2 セーフティドアスイッチ
3.2.3 トラップキー・インターロックシステム
3.2.4 セーフティライトカーテン
3.2.5 セーフティレーザスキャナ
3.2.6 感圧安全スイッチ(マットスイッチ、バンパースイッチ、テープスイッチ)
(b) 付加保護⽅策
3.2.7 非常停⽌スイッチ/ボタン
3.2.8 安全ロープスイッチ
3.2.9 動⼒遮断⽤ディスコンスイッチ
3.2.10 イネーブルスイッチ(グリップスイッチ)
3.2.11 セーフティリレー/セーフティコントローラ(安全 PLC)
3.3 使⽤上の情報提供
4 章 現場導⼊のメリットと具体的な事例
4.1 安全性向上によるメリットと効果
4.2 ディスコンスイッチ+トラップキー・システムの事例
4.3 ⽇本・欧州・アメリカにおける安全対策の事例
4.4 安全装置の設置・メンテナンスのポイント
5 章 まとめと今後の展望
2 20250321
1 章 はじめに
機械による作業の安全性確保は、企業にとって従業員を守る社会的責任であり、安定した⽣産活動の基盤でもありま
す。近年の統計でも、機械に起因する労働災害(機械災害)は全体の約 2 割を占め、製造業では約 4 割に達してい
ます。機械は強⼤なエネルギーを持つため、巻き込まれ・はさまれ等による重篤な負傷や死亡事故に結びつくケースが少なく
ありません。そのため企業は、「安全第⼀」の⽅針のもと、法令遵守と積極的な安全対策の導⼊によって労働災害防⽌に
努めることが求められます。また、安全な機械を提供することは製品の社会的信⽤にも直結し、企業の CSR(企業の社
会的責任)として重要視されています。
本ハンドブックは、⽇本の⼀般的なエンジニアの⽅々を対象に、機械安全の基礎知識と最新動向をわかりやすくまとめた
⼊門書です。親しみやすさも⼼がけ、現場で働く皆様が「明⽇から使える」安全知識を得られることを目的としています。具
体的には、機械安全の基本概念からリスクアセスメントの進め⽅、各種安全装置の役割と機能、導⼊によるメリット、国内
外の安全規格動向や最新技術まで網羅し、実際の⼯場・プラントで活⽤できるポイントを解説します。シンプルなイラストや
図を交え、実際の作業シーンをイメージしながら読み進められる構成としました。
まず冒頭では、安全対策における考え⽅の基本を確認し、企業が機械安全に取り組む意義を明らかにします。次に第 2
章以降で、機械安全の国際規格やリスクアセスメント⼿法、安全装置の種類と選定、実際の導⼊事例や効果について順
に紹介していきます。本ハンドブックが、職場の安全向上と安全⽂化の定着に少しでも役⽴つことを願っています。
労働災害による死傷者数・死亡者数
250,000 6,000
休 210,108 休業4⽇以上の死傷者数(左目盛り)
業 死亡者数(右目盛り)
200,000 5,000
四
⽇ 4,000
150,000
以 132,355
上 2,550 3,000
の 100,000
105,718 2,000 死
死 亡
傷 50,000 者
774 1,000 数
者 人
数
( 0 0
人
)
図 1. 労働災害発⽣状況 (1990 年~2022 年)
(出所:厚⽣労働省 HP 労働災害発⽣状況)
3 20250321
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
( )
2 章 機械安全の基本概念
2.1 安全とは何か? 機械災害の実態
安全とは単に「事故がない状態」を指すのではなく、人が安⼼して作業できる環境を計画的に作り出すことです。⾔い換
えれば、「許容できないリスクがない」ことと⾔えます。そして、人は注意⼒に限界がありミスを犯すもの、機械も故障し得るも
のだという前提に⽴つ必要があります。また「絶対安全」という状態は現実には存在しないため、万⼀ミスや故障が起きても
直ちに事故に結びつかないような対策が重要です。具体的には、「人の注意に頼る安全」から「機械や仕組みによる安全」
へと発想を転換し、エンジニアリングによってリスクを低減するアプローチが効果的です。
機械災害の実態を⾒ると、その多くは挟まれ・巻き込まれ、切断など重⼤な人体への被害を伴います。これは機械設備
が有する運動エネルギーや電気・油圧などの動⼒が人間にとって極めて危険なレベルだからです。例えば⾼速回転部への
挟まれ・巻き込まれ事故では、⼀瞬のうちに重傷を負う可能性があります。また、安全装置を無効化して作業していたため
に事故が起きるケースも後を絶ちません。こうした機械災害は適切な対策によって 「予防可能な事故」 であることが多く、
実際に機械メーカーがリスクアセスメントを実施して安全設計を織り込んだ機械を提供し、ユーザーが適切に安全装置を活
⽤すれば⼤部分は防⽌できるとされています。そのため、設計者と使⽤者の双⽅が協⼒して機械安全に取り組むことが重
要です。
本章ではまず、⽇本・欧州・アメリカにおける機械安全の法令や規格体系の概要を紹介し、続いてリスクアセスメント(危
険の特定・評価)とリスク低減の基本プロセスについて説明します。さらに、安全制御システムの信頼性指標であるカテゴリ
ー(Category)とパフォーマンスレベル(Performance Level, PL)の概念についても詳しく解説します。
図 2. 2023 年度 業種別労働災害発⽣状況 図 3. 製造業における休業 4 ⽇以上の発⽣原因
(出所:厚⽣労働省 HP 労働災害発⽣状況) (出所:厚⽣労働省 HP 労働災害発⽣状況)
4 20250321
2.2 ⽇本・欧州・アメリカの法令と国際規格
機械安全に関する法規制や標準は世界各地で整備されていますが、基本的な考え⽅は国際規格を通じて調和が進ん
でいます。⽇本では労働安全衛⽣法および関連法令により事業者に安全確保が義務づけられており、「機械包括安全指
針」(平成 19 年厚労省告⽰)などでリスクアセスメントの実施と安全⽅策の確⽴が推奨されています。特定の機械につ
いては安全基準が定められており、たとえばプレス機械についてはプレス機械構造規格があります。また JIS 規格として国際
規格を取り⼊れた安全規格(JIS B 9700=ISO 12100 等)が策定され、国内でも国際⽔準の安全設計が求められ
ています。
欧州では CE マーキングによって機械の安全基準適合が義務化されています。EU の「機械指令(2006/42/EC)」に
適合するため、ISO/IEC や EN の安全規格に基づいたリスクアセスメントと安全設計が求められます。代表的な国際規格
として、ISO 12100(機械類の安全設計の基本概念、リスクアセスメント原則)、ISO 13849-1(安全関連制御シス
テムの設計・PL の規定)、ISO 14119(インターロック機構の設計指針)などがあります。これらは EU の EN 規格とし
ても採⽤されており、CE マーキング取得のための技術的基準となっています。つまり欧州で機械を使⽤・販売するには、設
計段階からリスクを低減し各種安全装置を組み込んだうえで、適切な安全制御の性能(PL や SIL)を満たす必要があ
ります。結果として、欧州の⼯場では安全柵やインターロックスイッチ、非常停⽌などの安全措置が当たり前に導⼊され、⾼
い安全⽔準が保たれています。
アメリカでは OSHA(労働安全衛⽣局)の規則により機械ガードやロックアウト⼿順などの安全対策が義務付けられて
います。例えば OSHA 規則 29 CFR 1910.212 では、機械の危険部分にガード(防護物)を設置することが求められ
ています。またメンテナンス時のエネルギー遮断と施錠(ロックアウト・タグアウト、LOTO)は OSHA 1910.147 によって規
定され、作業者が修理中に機械が作動しないようにする⼿順が法律で定められています。ANSI(⽶国家規格協会)に
よる ANSI B11 シリーズの機械安全規格や NFPA79(産業機械の電気基準)などの産業規格もあり、これらは
OSHA 規則の遵守や安全対策のガイドラインとして広く参照されています。近年では ANSI 規格も ISO 規格と整合する
内容に改訂されており、例えば ANSI B11.0(機械の安全要求事項)は ISO 12100 とリスクアセスメントの考え⽅が
ほぼ同じになっています。このように、北⽶と欧州で規制体系は異なるものの、「機械の危険源を特定し、リスクを評価して、
適切な安全⽅策でリスクを許容可能な⽔準まで下げる」という基本プロセスは国際的に共通です。
ISO/IEC ガイド 51
ISO 機械系 IEC 電気系
機械類の安全性 -設計の⼀般原則- 基本安全規格
リスクアセスメント及びリスク低減 (ISO 12100) A 規格
( )
ガードインタロック(ISO14119/JIS B 9710)
スイッチ(IEC6094/JIS C 8201)
システム安全規格(ISO13849-1/JIS B 9705-1) 電気設備安全(IEC60204/JIS B 9960)
統合⽣産システム(ISO11161) グループ安全規格 人体検知⽤センサー(IEC61496/JIS B 9704)
ガードシステム規格(ISO14120/JIS B 9716) B 規格 機能安全(IEC61508/JIS C 0508)
非常停⽌機能(ISO13850/JIS B 9703) EMC(IEC61000-4/JIS C 61000)
安全距離規格(ISO13855,13857/JIS B 9715,9718) 防爆安全(IEC60079/JIS C 60709)
再起動防⽌(ISO14118/JIS B 9714)
両⼿操作制御装置規格(ISO13851/JIS B 9712)
個別機械安全規格
C 規格
図 4. 国際安全規格 ISO/IEC の体系図
5 20250321
2.3 改正安全衛⽣規則第 24 条 13、および、労働安全衛⽣法第 28 条の 2
改正安全衛⽣規則第 24 条 13 は、機械の設計・製造段階で実施すべきリスクアセスメントの結果に基づき、製造者が
機械に内在する残留リスクについて利⽤者に情報提供する義務を定めています。すなわち、製品の設計時に考慮されたリス
ク低減措置だけでは除去しきれなかった危険要因について、製造者はその性質や残存するリスクの⽔準、さらには対策⽅法
を明確にし、利⽤者が適切な使⽤・保守を⾏えるよう⽂書等で提供する必要があります。これにより、利⽤者は⾃社の作業
現場における安全対策の追加検討や運⽤⽅法の⾒直しが可能となり、事故防⽌に直結します。
⼀⽅、労働安全衛⽣法第 28 条の 2 は、事業者に対して、安全衛⽣に関する努⼒義務として、機械の設計・製造だけ
でなく、その使⽤状況に応じた適切な安全教育の実施や情報提供、そしてリスクコミュニケーションの強化を求めています。具
体的には、労働者が機械の危険性や残留リスクを正しく認識し、安全な作業環境を構築するために、事業者は定期的な安
全教育や訓練、並びに機械ごとのリスク評価結果を踏まえた使⽤上の指⽰を徹底しなければならないと規定しています。
これらの規定は、製造者と使⽤者双⽅に安全対策の責任を分担させ、全体としての事故防⽌効果を⾼めることを目的と
しています。製造者は残留リスクの情報を明確に伝え、使⽤者はそれをもとに現場でのリスク低減策を補完することが求めら
れており、いずれも合理的に予⾒可能な事故の防⽌に寄与する重要な法的枠組みです。
図 5. 改正安全衛⽣規則第 24 条 13 (引⽤: 厚⽣労働省 リスクアセスメント等関連資料・教材⼀覧より)
6 20250321
2.4 リスクアセスメントの⼿法
安全な機械システムを構築するには、体系的なリスクアセスメント(リスク評価)が不可⽋です。リスクアセスメントは⼤き
く以下の⼿順で⾏います。
開始
1. 機械類の制限の決定
リスクアセスメントを実施する際は、使⽤条件や環境、ユーザーの特性な 機械類の制限の決定
どを踏まえて「制限」を決定することが重要です。ISO 12100 では、制限
の決定を⼤きく以下の 3 つに分類しています。 危険源の同定
(a) 使⽤上の制限 分
リスクの⾒積り 析
・機械がどのように設置され、どのような目的のために使⽤されるのか。
・予⾒可能な誤使⽤を明確にする。 リスクの評価
(b) 空間上の制限
・機械の設置場所や周囲の空間、操作機器の配置を決め、⼗分な保
守作業や安全な作業環境を確保する。 リスクは適切に
(c) 時間上の制限 低減できたか︖
いいえ
・機械や構成部品の寿命や耐⽤期間を明確にし、適切な部品交換や はい
メンテナンス時期/頻度を定める。 終了 リスク対策へ
2. 危険源の同定 図 6. 機械安全のリスクアセスメントの⼿順
機械の構造や⼯程を洗い出し、どの部分にどんな危険(はさまれ、切断、感電、⽕災、有害光線など)が存在す
るかを明確にします。
3. リスクの⾒積もり
各危険について、事故が発⽣した場合の危害のひどさ(S: Severity)と発⽣確率や可能性(F: Frequency /
Probability)を評価し、リスクの⼤きさを⾒積もります(表 1. リスクマトリクスなどを使⽤)。
4. リスクの評価
⾒積もったリスクが許容可能か否かを判断します。法律や企業基準で「許容できない」とされるリスクについては低減
措置が必要です。
表 1. ISO/TR 14121-2 によるリスク⾒積もり(リスクマトリックス)
危害のひどさ 危害のひどさ 危害のひどさ 危害のひどさ
(特に重⼤) (重⼤) (中程度) (軽微)
発⽣確率
⾼ ⾼ ⾼ 中
(非常に⾼い)
発⽣確率
⾼ ⾼ 中 低
(⾼い)
発⽣確率
⾼ 中 低 わずか
(低い)
発⽣確率
低 低 低 わずか
(非常に低い)
7 20250321
2.5 リスク低減の 3 ステップ
許容できないリスクがある場合、設計者はそれを低減するための⽅策(リスク対策)を講じます。(このリスク対策はリスクアセ
スメントの⼀部ではありません。) リスク低減策を考える際には、ISO 12100 で推奨される「リスク低減の 3 ステップ(3 ス
テップメソッド)」に従います。この 3 ステップは後ほど3章で詳述しますが、まずは設計で危険を減らし、次にハード対策で
人を保護し、最後に情報提供でリスク認識を促すという三段階で対策を講じるのが基本となります。重要なのは、人間の
努⼒や注意⼒に頼るのではなく、機械側で安全を確保する策を優先することです。例えば、危険部分に誰も近づけないガ
ードを付けることは、「近づかないよう注意すること」と⼝頭で指⽰するより遥かに確実です。
リスクアセスメントと低減策の検討は、新規機械の設計段階はもちろん、既存設備の改善や変更時にも繰り返し⾏われ
ます。⼀度対策したから終わりではなく、現場でヒヤリハット(ニアミス)や新たなリスクが⾒つかれば再評価し、追加対策を
講じるというサイクルを回すことが⼤切です。最近ではこのプロセスを効果的に⾏うため、リスクアセスメント⼿法として
「HAZOP」や「FMEA」などの体系だった⼿法を⽤いたり、リスク計算ソフトウェア(例えばドイツ IPA の SISTEMA ツール)
を使って安全制御システムの性能評価を⾏ったりすることも普及してきました。また、ISO 45001 のような労働安全衛⽣マ
ネジメントシステム規格に沿って職場全体のリスク低減活動を継続的に進める企業も増えています。機械安全は⼀度きり
ではなく、常に改善・維持すべき継続課題なのです。
開始 3 ステップメソッド
による保護⽅策
危険源は はい
機械類の制限の決定 除去できるか? ステップ 1
本質的安全設 意図したリスクの低減
いいえ
危険源の同定 計⽅策 はできたか?
はい
リスクは本質的安全設計 はい
分 いいえ
リスクの⾒積り 析 で低減できるか?
いいえ
リスクの評価 ステップ 2
安全保護装置により低減 はい 安全防護 意図したリスクの低減
できるか? 負荷保護⽅策 はできたか? はい
リスクは適切に いいえ いいえ
低減できたか︖ ステップ 3
いいえ
制限の再設定は いいえ 使⽤上の情報 意図したリスクの低減
はい 可能か︖ による⽅策 はできたか?
はい
いいえ
はい
はい 他の危険源を
⽣じるか︖
いいえ
終了
図 7. ISO12100/JIS B9700 によるリスク低減⼿順
8 20250321
2.6 カテゴリー(Category)とパフォーマンスレベル(PL)の概念
2.6.1 カテゴリー(Category)
機械の安全対策を語る上で、制御システムの信頼性を⽰すカテゴリーとパフォーマンスレベル(Performance Level,
PL)という指標は重要な役割を果たします。これは主に、安全関連制御系(安全回路)が故障しても安全機能を維
持できる程度を表すものです。
カテゴリーは、もともと EN 954-1 という旧規格で定義されていた概念で、安全回路の構造上の分類を意味します。カ
テゴリーは B、1、2、3、4 の 5 段階があり、B が最も基本的な要求(最低限の構造)で、4 が最も⾼い安全要求を満
たす構造です。簡単に各カテゴリーの特徴を説明すると:
カテゴリーB: 基本的な安全原則に従って部品選定・設計された構造ですが、単⼀の故障が起これば安全機能は失わ
れます。要は最低限の安全構造です。
カテゴリー1: カテゴリーB の要件に加え、信頼性の⾼い部品を使⽤した構造です。それでも単⼀故障で安全機能は失
われますが、その発⽣確率が B より低い(壊れにくい部品を使っている)状態です。
カテゴリー2: カテゴリーB 相当の構造で、さらに安全機能が⼀定間隔で⾃⼰診断(チェック)される仕組みを持ちます。
⾃⼰診断の間隔内に故障が発⽣すると安全機能は失われますが、定期チェックによって故障の検出が可能
です。
カテゴリー3: カテゴリーB 相当の構造で、単⼀故障では安全機能が失われないよう冗⻑性を持たせています(例えば⼆
系統の独⽴した回路を⽤意)。可能な限り故障も⾃⼰検出する設計ですが、⼀部検出できない故障も残
り得ます。検出されない複数故障が蓄積すると安全機能を喪失する可能性があります。
カテゴリー4: カテゴリーB 相当の構造で、カテゴリー3 と同様に単⼀故障では安全機能を失わず、さらに故障が発⽣すれ
ば必ずそれを検出する(もしくは蓄積しても安全機能を喪失しない)よう設計されています。すなわち、あら
ゆる単⼀故障に耐性があり、連続する複数故障にも極めて⾼い信頼性で対処できる最上級の構造です。
カテゴリーB、カテゴリー1 の指定アーキテクチャ(構造)
I L O I ︓ ⼊⼒装置(例︓非常停⽌スイッチ)
L ︓ 論理処理
O ︓ 出⼒装置(例︓コンタクター)
I L O カテゴリー2 の指定アーキテクチャ
m m ︓ 監視
TE ︓ 試験装置
TE OTE OTE ︓ 試験装置の出⼒
m
I1 L O1
カテゴリー3、カテゴリー4 の指定アーキテクチャ(構造)
c
m m ︓ 監視
C ︓ 相互相監視
I2 L O2
図 8. 各カテゴリーのアーキテクチャ(構造)
9 20250321
2.6.2 パフォーマンスレベル(PL)
パフォーマンスレベル(PL)は、ISO 13849-1(2006 年版)で導⼊された新しい指標で、制御系の安全性能を
定量評価するものです。まず、PLr(必要パフォーマンスレベル)は、機械の安全性を確保するために、リスク評価に基
づいて安全関連制御システムが達成すべき最低限の性能を⽰す指標です。リスクの重⼤性や発⽣頻度に応じた安全
性能が求められ、その目標値をリスクグラフなどを⽤いて決定します。例えば危険度が⾼く頻度も⾼いリスクには PLd や
e が要求され、低リスクなら a や b で良いという具合です。 PLr リスク
a L
PLr 要求パフォーマンスレベル P1
・S 傷害のひどさ F1 P2
b
S 1 … 軽症(通常、回復可能な傷害)
S1 F2 P1
S 2 … 重傷(通常、回復不可能⼜は死亡)
1 P2
・F 危険源への暴露の頻度及び/⼜は時間 c
F1 … まれ ~ 低頻度、及び/⼜はさらされる時間が短い P1
F2 … ⾼頻度 ~ 連続、及び/⼜はさらされる時間が⻑い S2 F1 P2
・P 危険源回避⼜は危害の制限の可能性 c
F2
P1 … 特定の条件下で可能 P1
P2 … ほとんど不可能 P2 e
H
図 9. 要求パフォーマンスレベル(PLr)の決定⽅法 (ISO13849-1 リスグラフ法)
次に、安全関連制御システムが、設計された安全機能を⼀定の条件下で確実に維持できる能⼒を定量的に評価す
る指標であるパフォーマンスレベル(PL)を求めます。PL は a, b, c, d, e の 5 段階で表され、PL a が最も低く PL e
が最も⾼い安全性能となります。PL は以下の 4 つの要素によって決定されます。⼀般的には各部品の MTTFd、⾃⼰
診断機能(DC)、共通原因故障(CCF)の数値は、部品メーカーが提供する技術データシートや信頼性データ、テ
ストレポートから⼊⼿されます。これらの値は、メーカーによる実験や統計解析に基づいて算出されており、設計者はそれ
らを参考にして安全制御システム全体の評価を⾏います。
・ カテゴリー(上で述べた構造要件)
・ MTTFd(Mean Time To Dangerous Failure): 危険故障までの平均時間。要は部品の信頼性(寿命や
故障率)を表します。
・ DCavg(Diagnostic Coverage): 平均診断率。⾃⼰診断によって危険故障を検知できる割合です。
・ CCF(Common Cause Failure): 共通要因故障の考慮。冗⻑回路が共通の原因で同時に故障しないよう
対策されているかの評価です。
カテゴリー (B, 1, 2, 3, 4) カテゴリー、部品の信頼性、
システムの信頼性によって
MTTFd DCavg CFF パフォーマンスレベル(PL)
を決定する
図 10. パフォーマンスレベル(PL)の決定⽅法
10 20250321
以上をまとめて、ざっくり⾔えば、カテゴリーは構造上の指標、PL は構造+部品信頼性を含めた実効的な安全⽔準と⾔
えます。旧規格では「カテゴリー3 の回路だから安全」と表現していましたが、現在は「その回路は PL d を達成しているから
安全」という風に⾔います。なお SIL(Safety Integrity Level)という別の指標も IEC 61508/62061 で定義されて
おり、主に電気電⼦プログラマブル制御の機能安全を対象に SIL1〜4 の段階で安全度を評価します。産業機械分野で
は、欧州では PL(ISO 13849-1)が広く使われ、プロセス産業や⼀部電気制御では SIL(IEC 62061 など)が使
われますが、PL と SIL はある程度対応関係があり目的は同じです。
設計者は、機械の各安全機能について必要な PLr を決め、それを満たすように回路構成と部品選定を⾏います。例え
ば非常停⽌回路に PL c が求められるなら、カテゴリー1 の⼀部⾃⼰診断付き構成+⾼信頼性部品で⼗分か検討すると
いった具合です。PL の達成度合いは、メーカー提供のデータや専門ツールを⽤いて計算・検証します。結果として、機械全
体として必要な安全性能を満たしていること(PL 達成証明)が、CE マーキング等でのコンプライアンス宣⾔に不可⽋とな
ります。
現場のエンジニアにとっては「PL とか難しそう」と感じるかもしれません。ポイントは「安全装置を適切に選び正しく組み合わ
せれば、必要な安全レベルをクリアできる」ということです。近年はメーカー各社が安全設計をサポートする資料やツールを提
供しており、例えばカテゴリー4・PL e(最上級)相当の安全を達成する標準ソリューションとしてディスコンスイッチ+トラップ
キー・システムが注目されています。次章以降で安全装置の種類とともに、そうしたソリューションについても紹介します。
11 20250321
3 章 3 ステップメソッドに基づくリスク低減⽅策と安全装置の機能と特徴
この章では、機械のリスク低減に⽤いられる具体的な安全⽅策について、国際規格で推奨される「3 ステップメソッド」に
沿って解説します。すなわち、まず危険そのものを⼩さくする本質的安全設計、次に防護柵や安全センサーなどによって人
を危険から隔離・遮断する安全保護⽅策(安全防護措置)および非常停⽌などでそれを補完する付加保護⽅策、最
後に標識やマニュアルによる注意喚起といった使⽤上の情報提供です。それぞれのステップで代表的な安全装置や仕組
みを紹介し、その使⽤⽅法、特徴、および無効化(だまし込み)されるリスクと対策について述べます。
ステップ 1: 本質的安全設計
機械そのものの構造やエネルギーを⾒直し、根本的に危険を除去・低減する設計⽅策です。例えば、尖った部分を丸
める、可動部の質量や速度を下げる、人体が⼊り込むような⼩さな隙間をなくす、不要な危険機能を排除する、といっ
た措置が挙げられます。可能な限り危険源を設計段階で取り除くことが最優先であり、最も効果的なリスク低減策とな
ります。
ステップ 2: 安全保護⽅策および付加保護⽅策
ステップ 1 で除去しきれなかった危険に対し、ハード的な安全防護策でリスク低減を図る段階です。(a)人を危険から隔
離する安全保護⽅策(例︓固定式ガードやインターロック付き可動ガード、光電センサーなど)と、(b)それを補完する
付加保護⽅策(例︓非常停⽌スイッチ、イネーブルスイッチ、個人⽤保護具など)に⼤別されます。安全保護⽅策の
典型は防護柵による物理的な隔離や、安全装置が異常を検知して機械を停⽌させる仕組みです。⼀⽅、付加保護
⽅策は万⼀危険が発⽣した際に被害を最⼩化する措置で、非常停⽌や安全回路によるエネルギー遮断、保護具の
着⽤などが含まれます。技術的には、安全制御システムの設計(後述の安全リレーや安全 PLC の採⽤など)もこのス
テップに含まれます。
ステップ 3: 使⽤上の情報提供
ステップ 1・2 を講じてもなお残留するリスクに対し、注意喚起や安全な操作⼿順の指⽰を⾏う段階です。具体的に
は、危険箇所に警告ラベルを貼る、警報表⽰灯やブザーで異常を知らせる、取扱説明書に安全上の留意点を記載す
る、作業者に安全教育を施す、といったソフト対策が該当します。ただしこれらはあくまで最後の⼿段であり、ステップ 1・
2 で可能な限りリスク低減を⾏った上で、不⼗分な部分を補完するものです。警告表⽰やマニュアルは、作業者がそれ
らを守らなければ効果が出ないため、現場での周知徹底も重要になります。
以下では、上記ステップ 1〜3 に対応する各⽅策および関連する主な安全装置について詳しく⾒ていきます。
① 本質安全設計(機械を作り変える)
人 危ないモノや場所を無くす。安全なモノに置き換える。
② A.安全防護⽅策(安全装置を取り付ける)
ガード(隔離)
⼈人 危険 危ないモノや場所に触れないようにする。
⼈源
保護装置(停⽌)
⼈人 危険⼈源 動いている危ないモノや場所に触れないようにする。
② B.安全防護⽅策(安全装置を取り付ける)
⼈人 危険
⼈源 ガード、保護装置以外の安全装置で危険を避ける。
③ 使⽤上の情報(危険を避けてもらう)
危ないモノや場所に触らないようにするにはどうすれば
人 危険源
⼈ ⼈ よいかを分かるようにする。
図 11. 3 ステップメソッド
12 20250321
3.1 本質的安全設計
本質的安全設計とは、機械の構造・仕様そのものを⼯夫することで危険要因を可能な限り低減する設計⼿法です。
例えば、設計段階で挟まれや切断の危険がある部位の形状を変更したり、機械の出⼒や速度を必要最低限に制限
したりすることが挙げられます。エッジや角を丸めて怪我をしにくくする、動⼒を⼩さくして人に危害を及ぼさないようにす
る、など物理的・機能的に安全性を⾼める⼯夫です。また、人が⼊り込みそうな隙間をなくしたり、危険な動きを不要に
したりすることで、そもそも危険源を取り除きます。可能であれば危険そのものを完全になくす(例えば危険な⼯程を⾃
動化せず⼿動の安全な⼯程に変更する、余計な機能を削除する)ことが最善策です。これら本質安全の⼯夫により、
後述するガードやセンサーに頼る前にリスクの⼤部分を低減できます。 本質的安全設計の例としては、⼆重取っ⼿で
⼿を挟まない形状の⼯具設計、ロボットの動作範囲を物理的に制限するストッパの設置、摩擦クラッチで⼀定以上の
⼒が加わると空転してそれ以上の⼒を伝えない機構、電気設備で安全特低電圧(SELV)を採⽤して感電リスクを
下げること等が挙げられます。これらはいずれも機械の基本的な構造・仕様で危険発⽣の可能性を抑え込むアプローチ
です。ただし本質的安全設計にも限界があるため、取り除けなかったリスクについては次のステップで対処する必要があり
ます。
3.2 安全保護⽅策と付加保護⽅策
(A) 安全保護⽅策
安全保護⽅策では、防護柵や安全装置によって人を危険区域から遠ざけたり、危険が発⽣しそうなときに機械を停⽌
させたりすることでリスク低減を図ります。典型的には固定式ガードやインターロック付き可動ガードなどの「ガード(囲
い)」、光電式や圧⼒検知式の安全センサー類が該当します。これら安全保護⽅策により、作業者が機械の危険部
分に近づく前に機械の動作を停⽌させたり、物理的障壁で近づけなくさせたりすることができます。 まず、⽇本の産業現
場で広く使われている代表的な安全保護策である防護柵(ガード)とインターロック機器から説明します。その後、光
線式センサーや感圧式スイッチなど、人の存在や接近を検知して機械を⽌める安全装置について述べます。
3.2.1 固定式ガードと可動式ガード (関連規格: ISO 14119, ISO 14120, ISO13857)
(1) 使⽤⽅法と使⽤箇所 – 防護柵(ガード)は、人と機械を物理的に隔てることで危険接触を防ぐ最も基本的な安
全⽅策です。固定式ガードはボルト留めなどで容易に取り外せないよう固定された柵やカバーを指し、設備の内部に人
が⽴ち⼊る必要がない部分(ベルトやチェーンの駆動部覆い、装置外周のフェンス等)に⽤いられます。⼀⽅、可動式
ガードは開閉可能な扉やカバーで、材料のセットや段取り替えなど作業上どうしても人が⽴ち⼊る必要がある箇所に設
置されます。可動式ガードには通常インターロック装置(後述のセーフティドアスイッチなど)が取り付けられ、扉が開いた
ら機械を停⽌させる安全機能と組み合わせて使⽤します。固定式ガードは原則⼯具を使わなければ外せない構造と
し、可動式ガードも鍵付きやセンサー付きにして、作業者がガードを外したまま機械を動かすようなことがないようにしま
す。
(2) 特徴 – 固定式ガードは構造がシンプルで堅牢なため故障のリスクが低く信頼性が⾼い点が特徴です。常時危険部
を覆っているため、安全度も⾼くなります。可動式ガードは必要時に開閉できて作業性を損なわない利点がありますが、
その代わり扉の閉鎖を監視するインターロック機構を備える必要があります。国際規格 ISO 14120 や ISO 14119
では、ガードやインターロック装置について「容易に無効化できない」設計にすることが求められています。また、ガードの隙
間や開⼝部のサイズ・配置にも細かな基準があります。例えば、人体の指や⼿が⼊り込まないようにする最⼩すき間につ
いて JIS B 9711(ISO 13854)では「指先が届く箇所は少なくとも 25mm 以上、⼿が⼊る箇所は 100mm 以
13 20250321
上」など部位ごとの数値が規定されています。さらに、ガードの開⼝部越しに危険部まで⼿が届かない距離については
ISO 13857(JIS B 9718)で定められており、開⼝が⼤きいほど危険源から遠ざけて設置しなければなりません。
例えば柵の網目が⼤きい(約 50mm 以上)場合は約 850mm 以上離さないと腕が届いてしまう恐れがあり、逆に
細かい開⼝(12mm 以下)であれば指先しか⼊り得ないため 120mm 程度離せば安全、といった指針です。ガード
設計時には必ずこれら規格値を参照し、開⼝部から⼿⾜が⼊らない距離と⼗分な強度を確保する必要があります。
(3) 無効化リスクと対策 – ガードの主なリスクは、作業者による取り外しや開放のままの放置です。固定式ガードでも、
点検のために外した後できちんと復旧されなかったり、「⾯倒だから」と⼀部を外した状態で運転を続けたりすれば、防護
機能が失われてしまいます。可動式ガードの場合、インターロックが付いていても意図的なだまし⾏為によって無効化さ
れるケースがあります(詳細は後述のセーフティドアスイッチの項を参照)。これらを防ぐため、固定式ガードは⼯具なし
では外せない構造にする、取り外した際に元に戻さないと機械を起動できない仕組み(例えばガード⾃体にインターロッ
クを付けて外すと起動不可にする)を導⼊する、といった対策が有効です。可動ガードについても、鍵付きインターロック
や隠蔽配置(スイッチを外部から簡単に⾒えないよう設置する)など、無効化しづらい機器を選定します。また定期点
検でガードの取り付け状態やインターロックの動作確認を⾏い、異常があればすぐ修理します。管理⾯では「ガードを外
した状態で絶対に運転しない」というルールを徹底し、万⼀守られなかった場合の罰則を設けるなど、安全意識の周知
教育も⽋かせません。
(a) 囲いガード(引⽤:JIS B 9716) (b) 固定ガード(引⽤:JIS B 9716) (c) 可動式ガード(引⽤: JIS B 9700)
図 12. 固定式ガードと可動式ガード
14 20250321
■安全距離 (出所: JIS B 9718)
表 2. 構造物を超えての到達 上肢の安全距離 (低リスク)
危険区 保護構造物の高さ (b)
1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2500
域の高さ
危険区域への水平安全距離 (c)
2500 - - - - - - - - -
2400 100 100 100 100 100 100 100 100 0
2200 600 600 500 500 400 350 250 - -
2000 1100 900 700 600 500 350 - - - 危険区域
1800 1100 1000 900 900 600 - - - -
1600 1300 1000 900 900 500 - - - - 基準⾯
1400 1300 1000 800 800 100 - - - -
1200 1400 1000 500 500 - - - - -
1000 1400 1000 1000 300 - - - - -
800 1300 900 900 - - - - - -
600 1200 300 800 - - - - - -
400 1100 200 400 - - - - - - 保護構造物
200 1100 200 - - - - - - -
0 1100 200 - - - - - - -
注1)高さ1000mm未満の保護構造物は含まない。
それらは身体の動作を十分に拘束できないため。
注2)保護構造物なしの場合、危険区域への高さは 2500mm 以上が必要。
表 3. 構造物を超えての到達 上肢の安全距離 (⾼リスク)
保護構造物の高さ (b)
危険区域 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2500 2700
の高さ 危険区域への水平安全距離 (c)
2700 - - - - - - - - - -
2600 900 800 700 600 600 500 400 300 100 -
2400 1100 1000 900 800 700 600 400 300 100 -
2200 1300 1200 1000 900 800 600 400 300 - -
2000 1400 1300 1100 900 800 600 400 - - -
1800 1500 1400 1100 900 800 600 - - - -
1600 1500 1400 1100 900 800 500 - - - -
1400 1500 1400 1100 900 800 - - - - -
1200 1500 1400 1100 900 700 - - - - -
1000 1500 1400 1000 800 - - - - - -
800 1500 1300 900 600 - - - - - -
600 1400 1300 800 - - - - - - -
400 1400 1200 400 - - - - - - -
200 1200 900 - - - - - - - -
0 1100 500 - - - - - - - -
注 1)高さ1000mm未満の保護構造物は含まない。
それらは身体の動作を十分に拘束できないため。
注 2)1400mm よりも低い保護構造物は追記の安全方策なしで使用すべきではない。
注 3)保護構造物なしの場合、危険区域への高さは 2700mm 以上が必要。
15 20250321
■安全距離 (出所: JIS B 9718)
表 4. 開⼝部の安全距離 上肢の安全距離
安全距離 (Sr)
身体の部位 図示 開口部 (e)
⻑方形 正方形 円形
e≦4 ≧2 ≧2 ≧2
指先
4<e≦6 ≧10 ≧5 ≧5
6<e≦8 ≧20 ≧15 ≧5
8<e≦10 ≧80 ≧25 ≧20
指の関節までの指又は手 10<e≦12 ≧100 ≧80 ≧80
12<e≦20 ≧120 ≧120 ≧120
20<e≦30 ≧850 ≧120 ≧120
30<e≦40 ≧850 ≧200 ≧120
肩の基点までの腕
40<e≦120 ≧850 ≧850 ≧850
表 5. 開⼝部の安全距離 下肢の安全距離
安全距離 (Sr)
身体の部分 図示 開口部 (e)
⻑方形 正方形又は円形
つま先 e≦5 0 0
5<e≦15 ≧10 0
足指 15<e≦35 ≧80 ≧25
35<e≦60 ≧180 ≧80
足
60<e≦80 ≧650 ≧180
脚 [つま先から膝まで] 80<e≦95 ≧1100 ≧650
95<e≦180 ≧1100 ≧1100
脚 [つま先から股まで]
180<e≦240 許容不可 ≧1100
16 20250321
3.2.2 セーフティドアスイッチ (関連規格: ISO 14119)
(1) 使⽤⽅法と使⽤箇所 – セーフティドアスイッチは機械の危険エリアへのアクセ
スを制御するため、ガードの扉やカバーに取り付けられるインターロック⽤スイッチで
す。扉やカバーが開いたことを検知すると安全回路を動作させて機械を⾃動的
に安全停⽌させます。逆に⾔えば、扉が閉じてスイッチが正しく作動していない限
り機械が起動しないよう制御します。⼀般的な機械式タイプのスイッチでは、可
動部に直接開離機構(強制開路機構)を備えており、扉が閉まっていればス
イッチ内部で電気接点がオン通電しますが、扉を開けると機械的に接点を強制
的にオフ断路して電源を遮断します。産業⽤ロボットの囲い扉やプレス機のカバ
ーなどに広く使⽤され、作業者が危険部分へ侵⼊するのを防⽌します。 図 13. セーフティドアスイッチ
(2) 特徴 – セーフティドアスイッチには様々な種類がありますが、共通する特徴は堅牢な作りと確実な動作にあります。
多くの製品では機械式接点に強制開離機構が組み込まれており、スイッチがオンの状態で仮に接点が溶着して動作不
良になっても、扉を開ければ必ず回路をオフにできる安全設計です。また、防じん・防⽔性や耐振動性も⾼く、可動部
の位置ズレをある程度許容する調整機構を備えたものもあります。形状も様々で、鍵(アクチュエータ)を差し込むボル
トオンタイプ、蝶番と⼀体化したヒンジスイッチタイプ、非接触(磁気や RFID)タイプ、さらには電磁ロック機能付きタイ
プなどがあります。機械の停⽌時間が⻑い場合は電磁ロック付タイプを⽤いて「機械が完全停⽌するまでガード扉をロッ
クして開けられないようにする」ことで、余勢運動(停⽌直後の慣性で動く動作)による事故も防⽌できます。機械の
特性や要求安全レベルに応じて適切なタイプを選定できる柔軟性も、このスイッチの特徴と⾔えます。
(3) 無効化リスクと対策 – セーフティドアスイッチは、取り付けが不適切だったり簡易な原理のものだったりした場合、作
業者に意図的に無効化(だまし込み)されるリスクがあります。典型的なのは、扉を開けたまま予備のアクチュエータ
(鍵)を別途差し込んでスイッチを作動させ、機械を動かしてしまう不正操作です。このような無効化を防ぐため、ISO
14119 ではインターロック装置が容易に無効化されない措置を講じることが求められています。具体的には、特殊な形
状・符号化のアクチュエーターを使⽤して代⽤品を差し込みにくくすること、スイッチ本体とアクチュエーターを隠蔽配置して
簡単にアクセスできないようにすること、などの設計が推奨されます。また、定期点検時にスイッチ取り付け部が緩んでい
ないか確認し、確実に動作する状態を維持します。作業者への安全教育により「インターロックをだまして運転することは
重⼤な危険を招く」という意識を周知徹底することも重要です。さらに⾼度な対策として、安全ドアが閉まっていないと起
動できないだけでなく開放を検知すると警報が鳴る仕組みを追加したり、インターロック解除中は特別な安全モードでし
か動かないよう制御プログラム側で制限したり、といった⽅法も検討されます。
3.2.3 トラップキー・インターロックシステム (関連規格: ISO 14119)
(1) 使⽤⽅法と使⽤箇所 – トラップキー・インターロックシステムは、決められた鍵の抜き差し⼿順(シーケンス)によって
危険エリアへの⽴ち⼊りを制御する安全システムです。例えば機械の主電源スイッチ(後述する動⼒遮断⽤ディスコン
スイッチ)に専⽤の鍵付きユニットを取り付け、電源をオフにしないとその鍵が抜けないようにします。作業者は電源をオフ
にして鍵を抜き取り、それを持って移動し、今度はガード扉側のインターロックユニットにその鍵を差し込むことで扉のロック
を解除して危険エリアに⼊ります。つまり「電源を切る → 鍵を抜く → その鍵で扉を解錠」という⼿順を踏まなければ
危険区域に⼊れない仕組みであり、電源オフの状態でのみガードを開放できるようになります。このシステムは⼤型プレ
ス機や発電設備など複数の重⼤な危険源を持つ設備、あるいは広範囲の危険エリアでの保守・点検作業時によく⽤
いられます。
17 20250321
(2) 特徴 – 電気回路と機械的鍵の組み合わせによって⾼い安全性を実現している点が⼤きな特徴です。動⼒遮断
⽤スイッチ(ディスコン)を IEC 60947-3 適合品とし、トラップキー機構(ISO 14119 で規定)を組み合わせること
で、制御系の故障に影響されず直接主電源を遮断でき、最⾼⽔準の制御信頼性(カテゴリー4・パフォーマンスレベル
e 相当)まで構築可能とされています。機械的な鍵とシリンダー機構によるシーケンス制御で動作するため基本的に電
源不要で、環境的にも頑丈かつ⻑寿命です。鍵⾃体は厚い⾦属製で摩耗や破損に強く、システム全体が産業環境で
の酷使に耐える堅牢性を備えています。また、作業者が持ち歩く鍵そのものが「安全許可証」の役割を果たすため、鍵を
保持している限り機械を再起動できず、作業者の閉じ込め防⽌や誤再始動防⽌にも効果があります。
(3) 無効化リスクと対策 – トラップキー・システムは適切に設計・運⽤すれば非常に無効化されにくい仕組みですが、そ
れでも留意すべきリスクがあります。例えば予備の鍵を不正に作製・⼊⼿されてしまうと、本来の⼿順を踏まずに扉を開
けたり電源を投⼊したりできてしまう恐れがあります。また、鍵の戻し忘れや誤った順序での操作を⾏うと安全機能が働
かず事故につながりかねません。対策として、システムで使⽤する鍵とシリンダーは複製困難なユニーク形状のものを選
び、鍵番号の管理を徹底して予備鍵が勝⼿に出回らないようにします。製品⾃体も⾼強度・⾼耐久性で、意図的な
無効化を最⼩限に抑えた設計のものを選定する必要があります。運⽤⾯では、作業開始前に所定の電源オフと鍵抜
取りが確実に⾏われているか確認する⼿順を設けます。特に複数の作業者が関わる場合は、全員が⾃分のパーソナル
キー(作業者ごとに割り当てられた鍵)を持って作業に⼊り、全員の鍵が揃わないと機械を起動できないロックアウト⼿
順を導⼊するなど、安全管理を強化します。これらの対策により、トラップキー・インターロックシステムの無効化リスクを極
⼒低減し、確実に安全を確保することができます。
キー②
アクチュエーター
ド
ボルトインターロック キー① アインターロック
キー③
キー交換ユニット
ドアインターロック
南京錠でのロックアウト⽤の⽳を
利⽤してボルトインターロックする
図 14. トラップキー・インターロックシステム
18 20250321
3.2.4 セーフティライトカーテン (関連規格: IEC 61496-1, IEC 61496-2)
(1) 使⽤⽅法と使⽤箇所 – セーフティライトカーテンは機械の作業領域を光のカーテ
ンで囲み、人や⼿⾜がその光の幕を横切ると機械を停⽌させるタイプの安全センサー
です。発光部と受光部の間に⾚外線ビームが多数⾛っており、その⾒えないカーテン
を遮ると非常停⽌信号を出します。物理的な柵や扉とは異なり、光を使ったバリアな
ので作業者が装置に出⼊りする際に扉の開閉が不要です。このため作業効率を損
なわず安全を確保できる利点があります。主に産業ロボットの周囲やプレス機械の作
業エリアなどで、開⼝部を塞ぐ代わりにライトカーテンで⾒張るケースが多く、⼿をかざ
すだけで停⽌するため作業者にとっても扱いやすい安全装置です。
(2) 特徴 – 人体を検知するために複数の⾚外線ビームを平⾯状に張り巡らせてお 図 15. セーフティライトカーテン
り、⼿や指先まで検出できる⾼解像度タイプから、人体全体の侵⼊を検出する低解
像度タイプまでラインナップがあります。保護エリア(カーテンの⾼さ)のサイズも機種により様々で、必要な範囲をカバー
できるものを選択可能です。応答速度は数 ms〜数⼗ ms 程度と非常に⾼速で、危険部分との必要安全距離を短
縮できる場合があります。また、⽣産性向上のためミューティング機能(⼀時無効化機能)やブランキング機能(意図
的に⼀部のビームを無効化する機能)を備える製品もあります。例えばミューティング機能を使うと、ワーク(被加⼯
物)がライトカーテンを通過する際には停⽌信号を出さず、人が侵⼊した時のみ停⽌させることが可能です。これにより
⾃動搬送される部材の出し⼊れ中は機械を⽌めず、人が中に⼊ろうとしたときだけ停⽌させる柔軟な運⽤ができます。
⼀⽅、セーフティライトカーテンは発光部・受光部が正対するようにきちんと設置・調整する必要がありますが、可動範囲
の広い機械周囲ではミラーを⽤いてビームを屈折させ、側⾯からの侵⼊も検知できるようカバーする対策も可能です。非
接触で検知できるためオペレータの負担を増やさずに⾼い安全性を確保できる点も⼤きな特徴です。
(3) 無効化リスクと対策 – セーフティライトカーテンの主な無効化リスクは、意図的なセンサーの遮蔽や不適切な設置設
定による検知抜けです。前者の例として、作業者がライトカーテンの⼀部を板やテープで覆ってビームを常時遮光状態に
してしまうケースがあります。ビームが途切れたままだとセンサーは常に停⽌信号を出し続けるため機械は動きませんが、
⽣産現場ではこれを嫌ってセンサーに無断で細⼯し、常にビームが通った状態に⾒せかけてしまう(例えば発光部と受
光部を極端に近接させ、人が間に⼊っても遮光されないよう固定する)という悪質な無効化も起こりえます。当然なが
らこのような改造は重⼤な危険を招くため、管理者は現場パトロールや安全監査で不正なセンサー細⼯が⾏われてい
ないかチェックする必要があります。また、ライトカーテンの設置⾃体も安全専門家の指導のもとで⾏い、人がくぐり抜けら
れる隙間が上下左右にないか確認します。床⾯すれすれから所定の⾼さにビームを配置し、必要に応じて下部に人が
潜り込まないよう固定柵やバーを併⽤することも有効です。さらに、ミューティング機能を使⽤する場合は人が誤ってミュー
ティング中に侵⼊しないようセンサー配置やログ記録の確認など⼆重のチェックを設けます。定期的な清掃・点検も重要
で、光軸の汚れやずれによる検出性能の低下を防ぐためレンズ清掃と動作点検の記録を実施しましょう。以上の対策
により、セーフティライトカーテン本来の安全機能を確実に維持し、リスク低減効果を⻑く発揮させることができます。
19 20250321
3.2.5 セーフティレーザスキャナ (関連規格: IEC 61496-3)
(1) 使⽤⽅法と使⽤箇所 – セーフティレーザスキャナは、⾃ら発振し
た⾚外レーザ光を⽔平⾯内で扇状に⾛査し、物体からの反射光を
検出することによって周囲への人の侵⼊を感知する安全センサーで
す。所定の監視エリア内に人が⼊るか居続けると検知して停⽌信号
を出せるため、広範囲の危険源監視に適しています。例えば無人搬
送⾞(AGV/AMR)の前⽅障害物センサーとして、人や障害物と
の衝突防⽌に使われています。また産業⽤ロボットや⼤型⼯作機械
の周囲に⾒えない安全柵を作り出し、人が近づくと減速、さらに⼀定 図 16. セーフティレーザスキャナ
距離まで侵⼊すると停⽌といった⼆段階の安全制御にも活⽤されています。床に据え付けてエリア侵⼊を監視する⽤
途のほか、レーザスキャナを垂直に複数段配置して⽴体的な保護フィールドを作り出す応⽤例(例えば⾼所作業⾞の
上下にスキャナを配置して全体をカバーする等)もあります。広いエリアや複雑な形状の設備で、従来は柵やマットで人
を囲うしかなかった場⾯でも、レーザスキャナなら柔軟に安全領域を設定できるため重宝されています。
(2) 特徴 – 監視するエリアの形状や⼤きさをソフトウェア上で⾃由に設定・変更できる⾼い柔軟性が最⼤の特徴です。
曲線や複雑なポリゴン形状のエリアでもカバーできるため、機械レイアウトに合わせて無駄なく監視領域を決められます。
検出距離は機種によって数メートルから 10 メートル程度まで対応し、扇形に広がる検出角度は 180°から 270°程
度が⼀般的です。最新の製品では 270°・半径 8m 以上の保護エリアを持ち、1 台で広範囲をカバーできるものも登
場しています。また、警告エリアと保護エリアの⼆重設定が可能で、侵⼊物がまず警告エリアに⼊った時点で減速信号を
出し、さらに奥の保護エリア(危険エリア)に達したら停⽌信号を出す、といった段階的制御もできます。⾃⼰診断機
能も充実しており、レンズの汚れや受光異常があれば故障信号を出して安全側に制御する仕組みになっています。さら
に複数台のレーザスキャナをネットワーク接続して協調動作させたり、AGV の進⾏⽅向に応じて検知エリアを⾃動で切り
替えたりするような⾼度な使い⽅も可能です。このようにセーフティレーザスキャナは非常に⾼機能で柔軟な安全センサ
ーとして、様々なシーンで活⽤が広がっています。
(3) 無効化リスクと対策 – セーフティレーザスキャナは⾼度なセンサーですが、設置⽅法や設定の不備によっては検出でき
ない死角が⽣じるリスクがあります。⼀つはエリア設定の不適切です。例えば床上 50cm の⾼さで⽔平にスキャンしてい
る場合、しゃがんだ人の⾜先は検知できても、その人の上半⾝が既に危険エリアに⼊ってしまう可能性があります。このた
め必要に応じて上下に複数段のスキャナを配置したり、物理的ガードと組み合わせて死角をなくす設計にしたりすること
が重要です。また、⾼反射性または極端な低反射性を持つ対象物に対して検出性能が低下する場合があります。安
全レーザスキャナは光の⾶⾏時間測定や⾃⼰監視機能により材質差による影響を最⼩限に抑えていますが、鏡のよう
に反射するものや真っ⿊な物体では探知しづらいことを理解して配置する必要があります。意図的無効化については、
センサーの向きを変えて全く別⽅向を向けてしまう、電源⾃体を切ってしまう、といった極端な⾏為を除けば通常考えにく
いと⾔えます。しかし現場では「誤検知が多発して⽌まるのを避けたい」といった理由で勝⼿にソフト設定を変更し、検出
距離を短く再設定して遠くで人が⼊っても⽌まらないよう細⼯するといった改ざん⾏為のリスクはあります。これに対して
は、安全 PLC のプログラムや設定パスワードを管理し、現場担当者が無断でセンサー設定を変更できない仕組みにす
ることが有効です。また定期的にレーザスキャナのログや設定値を点検し、不審な変更がないか確認することも⼤切で
す。以上のように、最先端の安全センサーであっても油断せず、確実な設計・管理で安全機能を維持しましょう。
20 20250321